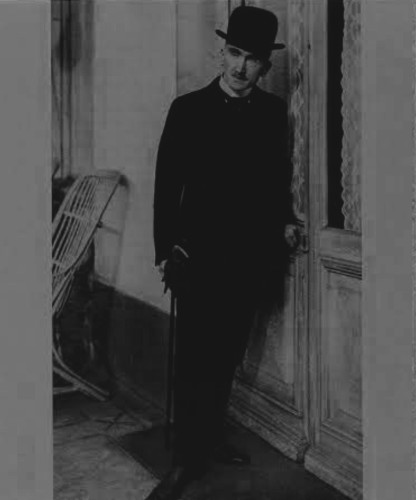
店主です。
アンリ・ベルクソンの『思考と動き』(La Pensee et le mouvant )を読んでいました。(もちろんフランス語のものではありませんが)。ベルクソンの本には、「時間」という概念がついています。どこを切っても、ついてまわっている印象があります。この著作にも独立した時間論がありますが、わたしがベルクソンに感じる時間というのは「文章そのもの」のことで、論説を待たないような種類のなにかです。とはいえわたしは「時間」というものがよくわかりません。「時間」というよりは「時間論」がよくわからないというべきかもしれません。自身の年齢にいくらかの符号がつけられるタイミングだったから、そんなことばかり考えていたのです。ベルクソンは「時」についての膨大な文献を残していますが、(まったく意味もなく個人的に)そういうものを追いかけていると、どこか首かしげの感覚に陥ります。そういうことが、よくあるのです。
一連の書きものをひろっていたわたしは途中で何だかあほらしくなり、「色無き緑の考え」というふうに、(おそらくすごい表情で)つぶやいていました。実際には、よく読めているとも思えませんでした。現代のわれわれから見返すと、ベルクソンの「時間論」というものは、何かずれているように感じます。決定的に、何かずれているように感じます。「簡単なことをただ難しく言おうとしているだけ」(チョムスキー)という気がするのです。しかし、ノーム・チョムスキーがジャック・デリダに向かって放ったことばと、わたしがアンリ・ベルクソンに対して思ったことと、いったいどこがどう似ているというのでしょうか。われわれは何かを言おうとするとき、あまりに「時」と「場合」というものを忘れがちです。なおかつ、前提条件をふいにしがちです。ベルクソンの「時間」は、あるパラダイムシフトでの前では意味がまるで違っていたはずのものです。わたしは彼の著作の意味よりむしろ、ある公理体系のあと(アインシュタインのあと)に、「時間」について語ることがほとんど「時計」について語ることと変わりがなくなった点について、あるいはそういう風にしか見えなくなった点について、注目すべきだと思います。そんなさなか、『思考と動き』と平行して読んでいたある本のうちに、(実際にいまここに書いていることとほとんどニュアンスが)同じことをすでに小林秀雄が言っていたのには驚きました。しかもそれは、相対性理論が出てからそれほど時間が経っていない頃にです。
「(時間というものを)説明しろといったら、わたしは、知らないと言う。説明しなくてもいいというなら、知っていると答える」(『告白録』アウグスティヌス)
わたしは、この「感覚」はどこかにあると思います。うまく言えないのですが、この「感覚」はどこかにあると思います。それは何かの公理系によってくつがえされるとか、何かのラショナリティ(合理性/理性感覚)によってくつがえされるとか、そういうものとは違うある「感覚」のことです。先日もずいぶん恥ずかしい思いをしましたが、わたしは、実際にコーヒーについて(かろうじて)何かくちにする場面にあると、だいたいいつもアウグスティヌス的な何かを感じています。じつに微妙な、アウグスティヌス的な何かを感じています。それは、「コーヒーというものを説明しろといったら、わたしは、知らないと言う。説明しなくてもいいというなら、知っていると答える」というような何かです。
ただ、このことについては、これ以上うまくいえません。
