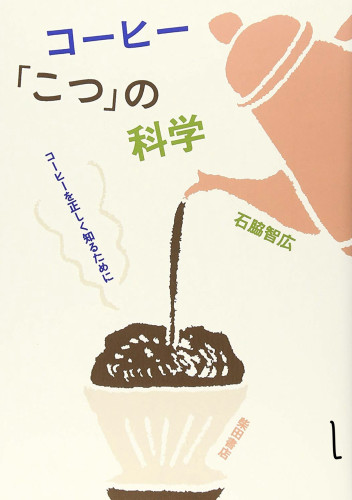
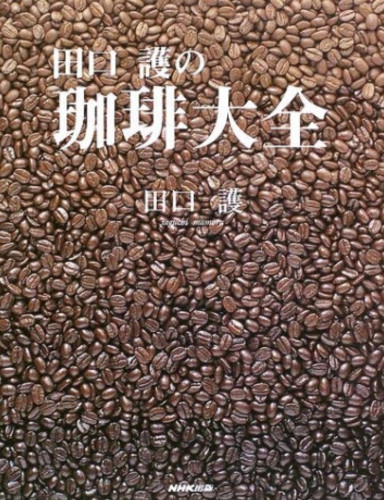
「コーヒーに関する本で何かお勧めはありますか?」
この質問をよくお受けします。
そのたび自分は変わらず『コーヒー「こつ」の科学』の名前をあげています。
10年後にも、同じことを聞かれたら、同じ本をお勧めすると思います。(コーヒー好きの方に配ったり、自分はいままでにこの本を個人的に30冊くらいは購入していると思います)。
良い本というのは、古びません。古びない本というのは、普遍性があります。
それは、単純にそのまま本の中に書いてある言葉が普遍的だという意味ではありません。もう少し言うと、書き手と言葉との関係性が普遍的なのです。
たとえば古びてしまう本は、その古び方において、形容詞がよく目立つようになります。それはたんに言葉として選ばれた形容詞が古さを帯びるというだけの意味ではありません。(たとえば固有名詞などは、時とともにもっとも形容詞化が進行しますよね)。
良い本の条件には、固有名詞が形容詞化する過程とはべつに、行間から形容詞の要素がわずかに顔をのぞかせる感覚があるのですが、それは時間がたってから見え方が変わります。まるで、生き物のようです。
『コーヒー「こつ」の科学』ののちに書かれた本で、この本よりも歴史言語学的に批判が届かなかったり、記述学的に精緻であったりする本は、「数冊」ほど出ていると自分は思います。しかし個人的には、それらは上記の「形容詞」の質的な点において、この本にはならばないと思います。
そしてゆいいつならぶものがあるとすれば、この本の数年前に書かれた『珈琲大全』だけではないかと考えています。
繰り返しますが、この2冊は極端な話、100年後でも再読に耐えうる本であると考えます。100年後に、ハンドピックという語がグレーディングやプレパレーション、ソーティングという語以外で呼ばれていたとしても、それは何も変わりません。これら2冊の本には、言葉の新しさによって獲得された刺激とは無縁の形で、書き手と言葉との関係性から来る「圧倒的な普遍性」があると思うのです。
